豆腐を使った料理をする時に必要なもの、水切り。
あなたは、豆腐の水切りがなぜ必要かご存知ですか。
調理中の型崩れ防止のためと、味を染み込みやすくさせるためです。
ところが、豆腐を水切りする目的は知っていても、水切りはしないという人は少なくありません。

水切りは時間がかかって面倒だし、仕上がりに差はないような気がする…。
確かに、豆腐を水切りしてもしなくても、さほど変わりがないような気がしますよね。
しかし水切りしないままだと、せっかくの豆腐料理が台無しになってしまうことがあるのです。
この記事ではなぜ豆腐の水切りが必要なのか、その理由と簡単な水切りの方法、水切りなしでも美味しい豆腐料理をご紹介します。
豆腐の水切りは面倒で省略しているというあなたは、ぜひ参考にしてみてください。
豆腐の水切りはなぜ必要?豆腐からなぜ水は出るの?

なぜ、豆腐は水切りが必要なのでしょうか。
豆腐を水切りすると、豆腐に含まれる水分が放出されて味が染み込みやすくなり、また型崩れしにくくなります。
豆腐を使ったメニューって、本当にたくさんありますよね。
冷奴に湯豆腐、麻婆豆腐や豆腐ハンバーグ。
お味噌汁の具にしてみたり、揚げ出し豆腐にしてみたり。
そんなレパートリーが多い豆腐は、とても柔らかく崩れやすい食材です。
水切りをしないでそのまま煮込むと、味が染み込む頃には煮崩れてしまいます。
ですので、水切りをすることで短時間で味が染み込むようにし、さらに型崩れもおこしにくくしておくというわけなのです。

家族が食べるだけだから、多少、煮崩れてしまってもいいわ
そうですよね。
家庭料理に完璧な見た目は必要ないですよね。
ところが、「豆腐を少し煮込んだだけなのに、なぜか食べる頃には水っぽくなってしまった」という経験はありませんか?
豆腐のおよそ90%近くは水分なので、煮込むとその水分が出てきて水っぽくなってしまうのです。
豆腐の水分は、木綿豆腐で86.8%、絹ごし豆腐で89.4%も含まれています。
豆腐は、いわば水をたっぷり含んだタンパク質のスポンジ。
スポンジのように水分をたっぷり含んだ豆腐を料理に入れれば、水っぽくなってしまうのは当然ともいえます。
豆腐の水切りは、このスポンジの水分を減らしてそこに味を染み込みやすくするため、必要なのです。
豆腐の水切りが簡単にできる方法4つ!

豆腐の水切りをしっかりとすれば、味がしみこんで料理がおいしくなるのですが、簡単に水切りができる方法があれば時短になりますよね。
では、どんな方法で水切りすれば、簡単にしっかりと水分を抜くことができるのでしょうか。
<豆腐の水切りをする4つの方法>
- 電子レンジを使う
- 重しをする
- 湯通しする
- そのまま放置
順番に詳しくご紹介します。
豆腐の水切りは電子レンジを使えば大幅時短!!
私がおすすめするのは、最も時間のかからない電子レンジを使う方法です。
パックから出した豆腐をキッチンペーパーで包んだら耐熱皿に置き、ラップをしないで600Wのレンジで2〜3分加熱。
しっかり水切りしたい場合は、重しをのせてしばらく放置します。
ただしレンジの機種や豆腐の大きさ、種類によっては加熱のしすぎで内部にスが入ってしまうことがあります。
豆腐にスが入ると食感が悪くなってしまうので、この場合は豆腐を潰して豆腐ハンバーグやそぼろなどに使うようにしましょう。
不安な場合は時間を短くして様子を見ながらやってみたり、ワット数を低くしてみるのがおすすめです。
何度か挑戦してみて最適な加熱時間を見つけましょう。
重しを使って豆腐の水切り
豆腐を水切りする方法で最も一般的なのは重しをすること。
豆腐に熱を加えないので、白和えやサラダを作るときにおすすめの方法です。
手順はとっても簡単。
レンジを使うときと同じように豆腐をキッチンペーパーに包んで、重しを乗せて30〜60分放置するだけ。
重しにはお皿やバットが適しています。
キッチンペーパーで包んだ豆腐の上にお皿やバットをのせ、その上に水を入れた鍋やボウルを置くといいですよ。
お皿もバットも平らなので、豆腐に変な型がついてしまうのを防ぐことができます。
ただし、重し代わりに置いたボウルや鍋が不安定だと、水がこぼれてキッチンが水浸しになってしまう危険がありますので、要注意です。
豆腐は湯通ししても水切りできる
豆腐をお湯でゆでて水切りする方法です。
豆腐がかぶるくらいの量の沸騰したお湯に豆腐を入れ、5分くらい弱火で湯がいたら、ザルに上げて完成。
しっかり水切りしたい場合は、ザルに上げた後キッチンペーパーで包んで重しをのせておけば大丈夫。
豆腐を温めて水切りするので、調理中に温度が下がらないというメリットがあります。
湯通しの際に豆腐の風味が流れ出やすいので、麻婆豆腐や豆腐チャンプルーなど濃いめの味付けの料理の時におすすめの方法です。
究極のズボラ技!パックのまま放置!?
なんと、豆腐をパックのまま水切りしてしまう方法があります!
パックの一箇所に包丁で5センチほど切り込みを入れ、切り込み部分が下になるようにひっくり返して、お皿やタッパーに置き冷蔵庫で一晩放置。
たったこれだけです。
時間はかかりますが、「明日、豆腐を使うぞ」と前日に分かっていれば、放置するだけなので簡単ですね。
豆腐を水切りしないまま使えるのはどんなメニュー?


豆腐の水切りをするとおいしく料理が出来上がるのは分かったけど、時間がない時は省略したい…。
そんなあなたに、豆腐を水切りしないまま使っても美味しいメニューをご紹介します。
冷奴や揚げ出し豆腐
豆腐独特のトゥルンとした舌触りやなめらかさ、柔らかさを味わいたいときは、水切りしないまま使うことをおすすめします。
冷奴も揚げ出し豆腐も、豆腐自体に味を染み込ませるのではなく、醤油やめんつゆをかけたり、濃いめに味つけたあんをかけたりして食べるものですね。
かける調味料やあんの量で味の濃さを調節できますし、お好きな薬味をかければ味の変化も楽しめます。
もちろん、水切りした豆腐で作ることもできますよ。
水切りをすると豆腐自体の味が濃くなり、少し固くなるのでお箸でも食べやすくなります。
また型崩れもしにくくなるので、調理の時に扱いやすくなります。
柔らかくトゥルンとした豆腐の食感を味わい時は水切りなしで、濃い味の豆腐を味わいたい時は水切りをして、と使い分けてもいいですね。
お味噌汁
お味噌汁に入れる豆腐も水切りなしで充分おいしくできます。
水切りなしの豆腐を味噌汁に入れる時は、味噌を溶いて味を決める前に豆腐を入れます。
豆腐を入れる前に味噌を入れて味を決めてしまうと、豆腐から水分が出て味が薄くなってしまいます。
だし汁に豆腐以外の具材を入れ、火が通ったら豆腐を入れてひと煮立ち。
それから、味噌をといて味を決めましょう!
お味噌汁の隠し味については、こちらの記事で紹介されていますので、ぜひ試してみてください。
麻婆豆腐
麻婆豆腐も少しの工夫で湯通しなしでおいしく食べられます!
麻婆豆腐のレシピには大抵豆腐を水きりすると書かれていますが、お味噌汁のときと原理は同じ。
- ひき肉やネギなどの具材を炒める
- 小さく切った豆腐を入れ、ひたひたの水を注いだら沸騰させる
- 弱火で3分ほど煮立たせた後で、味見しながら味付けをする
豆腐を鍋に入れてしばらく煮立たせることで先に豆腐から水分を出し、その後味付けをします。
そうすると麻婆豆腐が水っぽくなってしまうのを防ぐことができます。
調理中に豆腐を煮立たせて湯通しをすれば水切りをしたことになるため、水切りが必要ないということですね。
そして、最後に味を決めればおいしい麻婆豆腐の出来上がりです!
まとめ

- 豆腐は水切りすると味が染み込みやすくなり、型崩れも防ぐことができる
- 豆腐のおよそ90%は水分なので、豆腐を水切りしないまま調理すると水っぽくなってしまう
- 豆腐の水切りには、レンジ加熱、重しをする、湯通し、そのまま放置、の4つの方法がある
- 電子レンジを使って、豆腐を水切りすれば時短に
- 料理の種類のよっては、水切りしないままの豆腐を使うことができる
- 前もって水切りをしておかなくても、豆腐を加えてから味を付けることで、水っぽくなるのを防ぐことができる
豆腐の水切りは、大切な工程だったのですね。
水切りをしない場合は、味を見ながら最後に味付けすれば、水っぽくなるのを防ぐことができるという時短ワザはぜひ使ってみてください♪
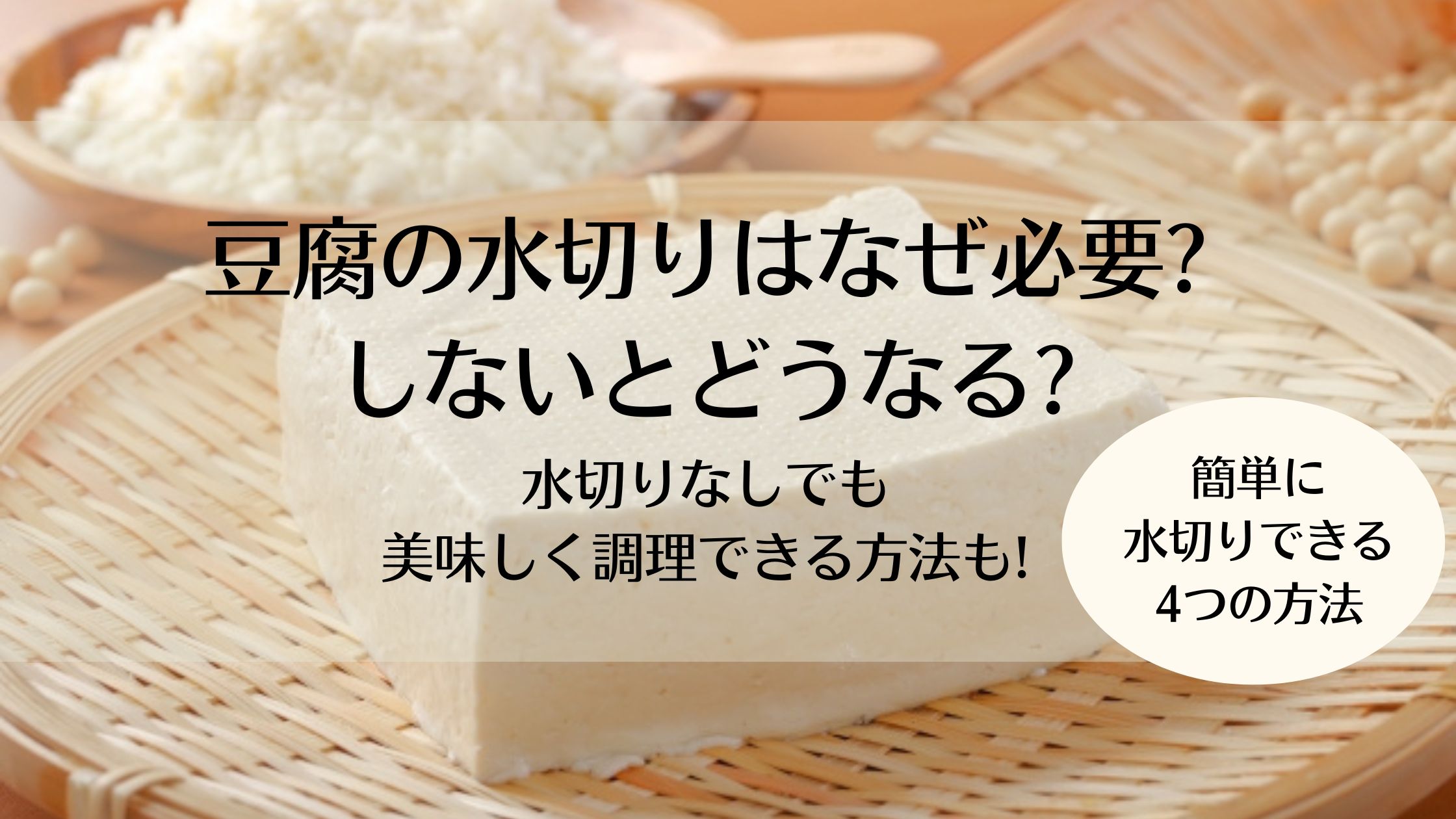



コメント