最近、家庭の食事でもよく見かけるローストビーフ、おいしいですよね。
カットした断面は薄いピンク色で、食べると半生な感じで柔らかい。
この半生な感じのローストビーフ、ちゃんと火が通っているか心配になりませんか?
見分け方にはいくつかあって、断面を見る、肉汁で判断する、肉に刺した串を唇に当てる等どれも簡単な見分け方で判断がつきますよ。
もちろん調理用の温度計で計るといった確実な見分け方もあります。
せっかく作ったのに生焼けだったときは残念ですし、半信半疑のままで食べたら食中毒も心配です。
しかし生焼けの状態のローストビーフも再加熱すれば、美味しく食べられますよ!!
今回はローストビーフの生焼けの見分け方と、生焼けを再加熱して美味しく食べられる方法をご紹介します。
ローストビーフが生焼けだった時の見分け方とは!?
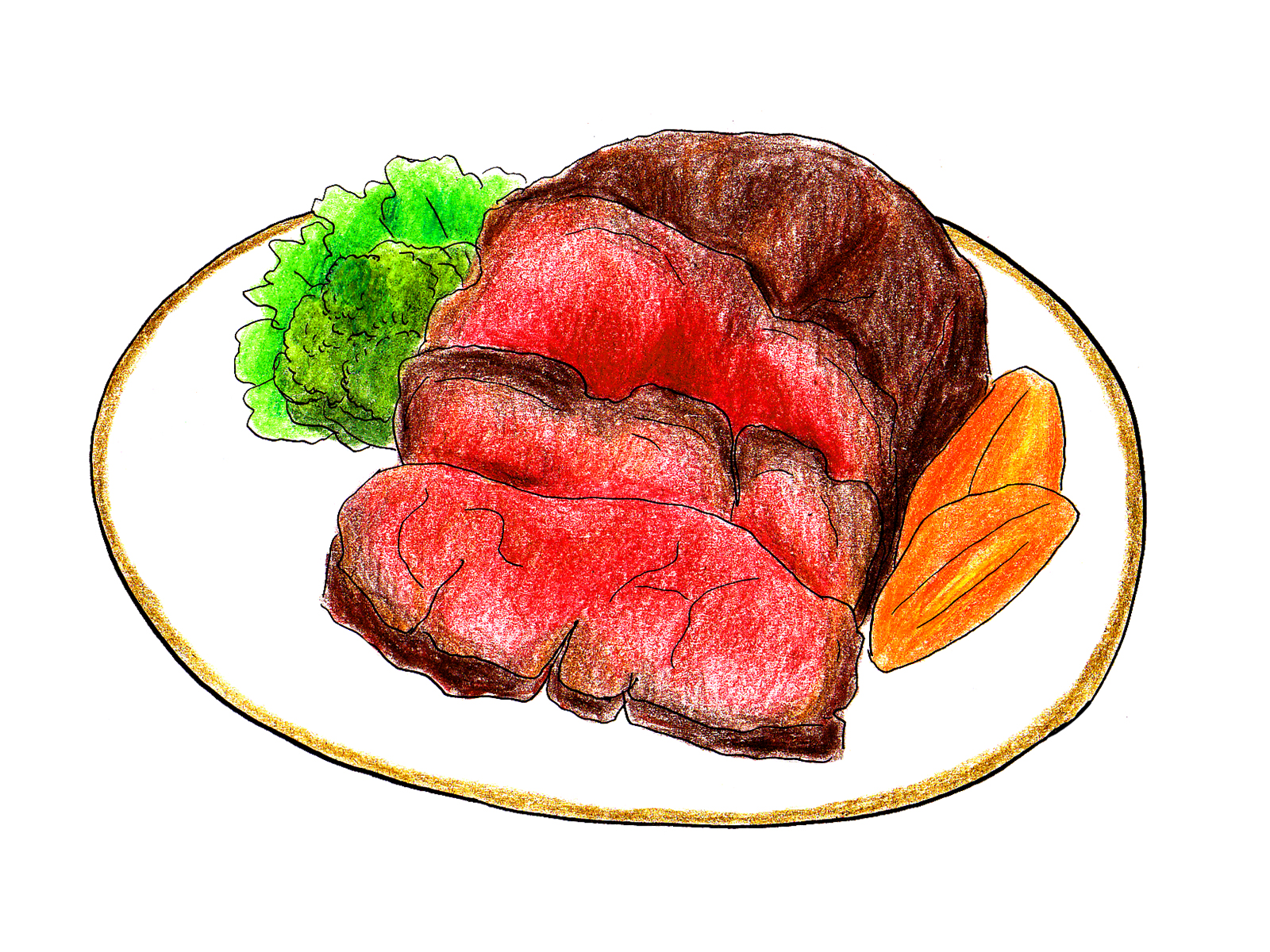
断面がうすいピンク色でしっとりとしたローストビーフは、とてもおいしそうですよね。
しかし火が通った状態なのか、生焼けの状態なのかはっきりわからなくて心配になるときはありませんか?
生焼けのではないかと火を通しすぎると、せっかくのローストビーフがパサパサになっておいしくありません。
このような時に生焼けか、火が通っているかの見分け方を知っておくと安心ですね。
ここからはローストビーフが生焼けかどうかの見分け方、そしてローストビーフが生焼けになる原因をお話しします。
ローストビーフをカットして断面を見てみましょう
出来上がったローストビーフをカットして、断面を見てみましょう。
火が通った状態のローストビーフの断面は、薄いピンク色をしています。
生焼けの状態とは違ったロゼというピンク色で、火が通っている証拠です。
柔らかく肉汁が十分詰まったローストビーフに仕上がっています。
カットしたばかりのローストビーフの断面はピンク色ですが、時間をおくと赤い色に変わっていくのですよ。
これは肉の中のヘモグロビンという成分が、酸素に触れて赤くなるので生焼けの状態とは違います。
お店で売られているローストビーフの断面が赤いのは、この変化によるものなので安心してくださいね。
金串を刺して温度を確かめてみましょう
まずローストビーフの中心部分に金属の串を刺して10秒ほど待ってから抜きます。
この金串を下唇に当てて、温かいと感じたら火が通った状態です。
このあたたかく感じる状態は、だいたい50℃~60℃位になっているのですよ。
しかし下唇に当てた時に、冷たい、ぬるいと感じたら十分火が通っていない生焼けの状態。
逆に熱いと感じた時は、残念ですが火が通りすぎてしまったことになるのです。
焼いた後の肉汁で判断できます
ローストビーフができあがったら、厚みのある部分に箸や串を刺してみましょう。
箸や串を抜いた後、肉汁が出てきますよね。
その肉汁が透明または薄い赤なら火が通った証拠です。
この赤色は血の色とは違うので、判断付きやすいですよ。
反対に生焼けの状態だと、血の色の肉汁が出てきます。
調理用の温度計で計りましょう
飲食店などでは食中毒防止のために、調理後には必ず食材の中心に温度計を刺して温度を計ります。
一定の温度に達すると、熱で菌が死滅するので食中毒の防止になるのです。
この温度計を使うと、ローストビーフをカットしなくても生焼けかどうか見分けができますね。
ローストビーフの場合は、中心部分に温度計の先を刺して54℃~57℃に達していれば火が通った状態といえます。
カットした時にちょうど良いピンク色のロゼになっていますよ。
また50℃以下だと生焼けの状態、60℃以上だと火が通りすぎた状態になります。
ローストビーフが生焼けになる原因は下準備にある!?
ローストビーフが生焼けになるのはなぜでしょう?
まずは調理の準備段階から見ていきましょう。
ローストビーフを焼く前には牛肉を常温に戻しておく必要があります。
冷蔵庫から出したばかりの牛肉は冷たいですよね。
このまま冷たい牛肉を焼くと、なかなか中心部の温度が上がりません。
中心部の温度が上がるまで焼いていると、表面だけが焦げ付いてしまいますよね。
そして中まで火を通すのに時間がかかると、おいしい肉汁がどんどん出ていくことになるのです。
さらに焼いた後の余熱時間が短くても、生焼けの原因になります。
肉の厚みによっても時間は変わるので注意しましょう。
余熱を通すときは、アルミホイルでローストビーフ全体を包むと効率的に熱が伝わりますよ。
ローストビーフが生焼けだった時は再加熱できます!!

ローストビーフが出来上がったと思ってカットして見たら、生焼けで血の色の肉汁が出てきた時はとても残念ですよね。
そのような生焼けのローストビーフでも、再加熱すれば美味しく食べることができます!
ただ、再加熱したら火を通しすぎてパサパサになってしまうのでは、と心配になりませんか?
生焼けのローストビーフにもいろいろな状態があります。
そのローストビーフの状態に応じて、再加熱のやり方を選ぶことができるのです!!
状態に応じた再加熱のやり方で、おいしいローストビーフに仕上げましょう。
表面に焼き色がついていない時はフライパンで
最初の調理でそれほど焦げ目がついていなかった場合は、フライパンを使う再加熱がおすすめです。
フライパンを熱くして、油を少し入れて生焼けのローストビーフを入れます。
フタをして弱火で5~10分蒸し焼きにしていきましょう
出来上がったら皿にローストビーフを取り出して、しっかり粗熱が取れるまで待ちます。
おいしそうな焼き色も付きますし、生焼けも解消できる、一石二鳥ですね。
表面に十分焼き色が付いている時は湯煎で
焼き色が十分ついていて、これ以上焦がしたくない場合は湯煎で再加熱しましょう。
最初にローストビーフをラップで二重にくるみます。
次にお湯が入り込まないように、ジッパー付きの袋に入れましょう。
この時、できるだけ袋から空気を抜いて真空状態にすると、火の通りが均一になりますよ。
次に大きめの鍋にたっぷりのお湯を沸かします。
お湯が沸いたら火を止めて、鍋の中にジッパー付きの袋に入れたローストビーフを入れます。
ここではローストビーフ全体がお湯に浸かっているかどうかがポイントになります。
ローストビーフが浮いてきてしまう場合は、落し蓋をすると防げますよ。
そのまま約10分置いておきます。
生焼けの状態や肉の厚みにもよりますが、最大で約20分鍋の中に入れておけば出来上がりです。
電子レンジで再加熱する方法
ローストビーフの表面がどのような状態でも再加熱できる方法が、電子レンジです。
まずはラップに包んでから電子レンジに入れます。
肉汁が出てくるかもしれないので耐熱皿の上に置いてから入れると安心ですね。
電子レンジ200wで2分ほど加熱します。
肉の断面を見ながら加熱時間の調整をしましょう。
加熱時間を追加するときは、10秒ずつくらい肉の様子を見ながら調整すると火の通しすぎを防ぐことができますよ。
取り出すときはローストビーフがかなり熱くなっているので、火傷をしないように気を付けてくださいね。
時間のある時は炊飯器で再加熱する方法もあります
少し時間に余裕があるときは、炊飯器を使って再加熱をする方法もあります。
最初にローストビーフをラップで巻いて、ジッパー付きの袋に入れます。
この時も袋の中の空気はできるだけ抜いて、真空状態にしましょう。
炊飯器にローストビーフが浸るくらいの量のお湯を入れます。
この時、お湯の温度は70℃くらいを目安にしましょう。
お湯の中にローストビーフを入れます。
約40分間、保温状態で待ちます。
ローストビーフを取り出して、冷まして出来上がりです。
少し時間はかかりますが、火加減の調節などが必要ないので便利ですね。
ローストビーフの生焼けは食中毒にならないの!?
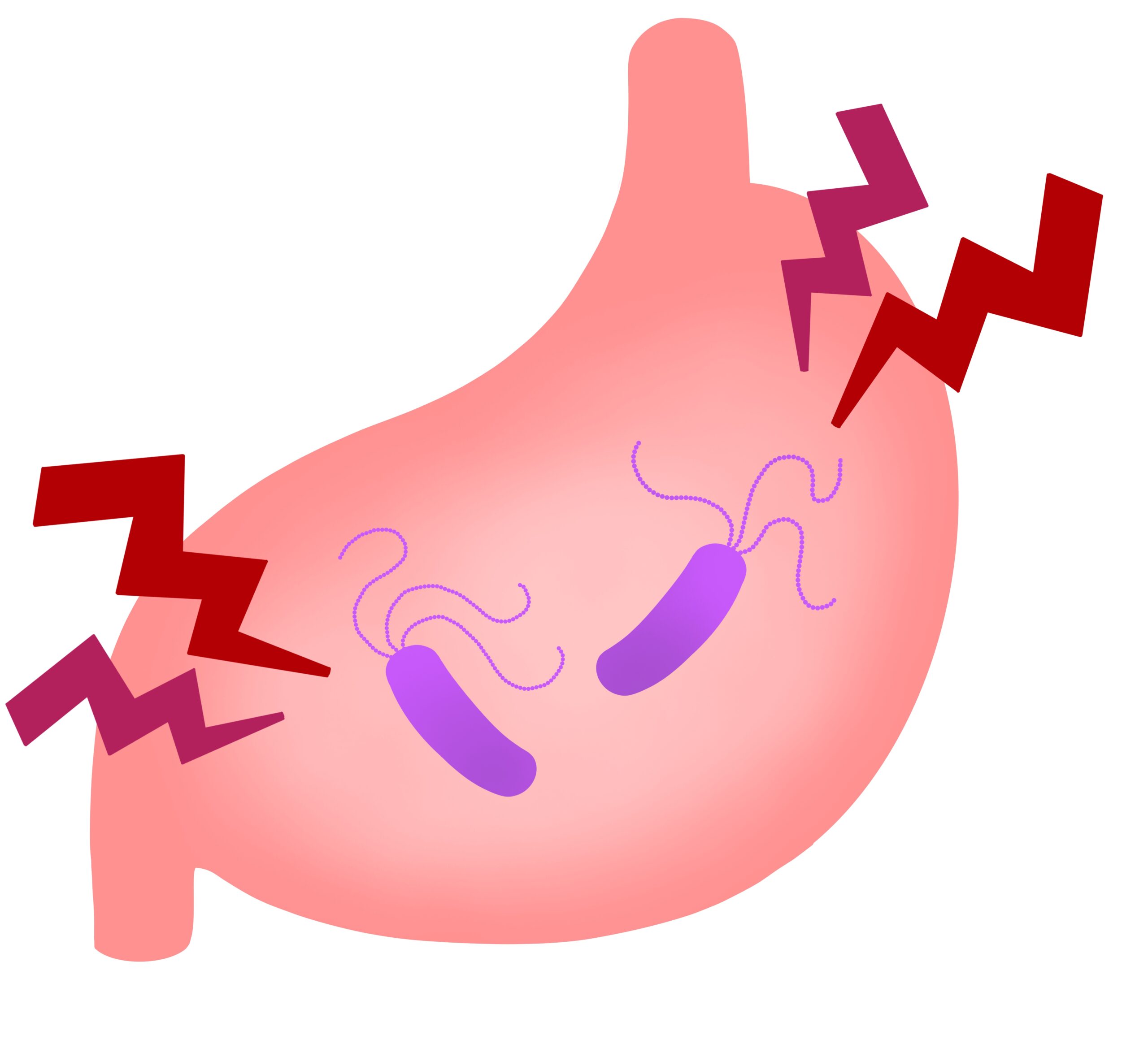
微妙な焼き加減のローストビーフ。
万が一、生焼けの状態で食べてしまったら食中毒になるのでは、と心配になりますよね。
しかし調理方法を守って作った牛肉の料理は、ほとんど食中毒の心配はありません。
ではなぜ牛肉は食中毒の心配が少ないのでしょう?
また安全に食べられる調理法とはどんなやり方なのでしょうか?
ここではローストビーフの生焼けを食べても食中毒にならない場合と、食中毒になる可能性がある場合を見ていきましょう。
ローストビーフの生焼けは食中毒にならないの!?
牛肉に存在する菌は、表面についている菌がほとんどだといわれています。
その為、調理の時に表面をしっかりと焼いておけば表面についた菌は、ほぼ死滅するので食中毒になる可能性は低いのです。
また、牛肉の内側には人に害を与える菌や寄生虫もいないとされています。
ただ、これは牛肉だけにいえることです。
その他の豚肉や鶏肉は、人の健康を害する細菌が付いている可能性が高いので調理するときは十分気をつけましょう。
食中毒になる原因は牛肉の取り扱い方!?
ローストビーフが生焼けの状態でも、しっかり表面を焼いて菌を死滅させておけば食中毒の可能性は低くなります。
しかし表面の菌を死滅させても食中毒になる原因があります。
その原因は牛肉の賞味期限が切れている、保存状態が悪く行肉の表面が変色しているなどです。
このような状態の牛肉を生焼けで食べてしまうと食中毒の症状が出る時があるので気をつけましょう。
また調理する際に手袋をしないで牛肉に触って、手を洗っても何かしらの原因で口に入るかもしれません。
牛肉の表面についた菌が口に入る事になるので、手袋をつけてから調理する事をお勧めします。
食中毒の症状としては、腹痛、下痢、嘔吐、発熱などがあります。
このような症状が出た場合は重症化する恐れもあるので、早めに受診するようにしましょう。
まとめ

- ローストビーフの生焼けの見分け方はカットした断面の色、肉汁の色などで判断できまよ
- 温度での見分け方は中心温度が50度に達していない時です
- 見分け方にはほかに金串を唇に当てる方法もあります
- 常温に戻さずに調理するとローストビーフが生焼けになりやすいですよ
- ローストビーフが生焼けだった時は、焼いた後の余熱時間が不十分だったことも原因です
- ローストビーフが生焼けだった時は、再加熱して美味しく食べられますよ
- 生焼けだったローストビーフを食べても表面が焼けていれば食中毒になる可能性は低くなります
- 牛肉の保存状態が悪いと表面を焼いても食中毒になる可能性がありますよ
ローストビーフは、断面の色や肉汁の色、温度などいくつかの方法で生焼けかどうかを見分けることができますよ。
まずは生焼けのローストビーフにならないように、調理前に牛肉を常温に戻しておくことや焼いた後の余熱時間を十分とることを忘れないようにしましょう。
もしローストビーフが生焼けだった時でも、フライパンや湯煎など出来上がったローストビーフの状態に合わせた再加熱のやり方で美味しく食べることができますよ。
牛肉の表面を十分に焼くと菌が付いていてもほとんど死滅するので、食中毒のリスクは低くなります。
しかし牛肉の保存状態や扱い方で食中毒になる率は高くなってしまうのです。
調理方法に気をつけて美味しいローストビーフを作りましょうね。
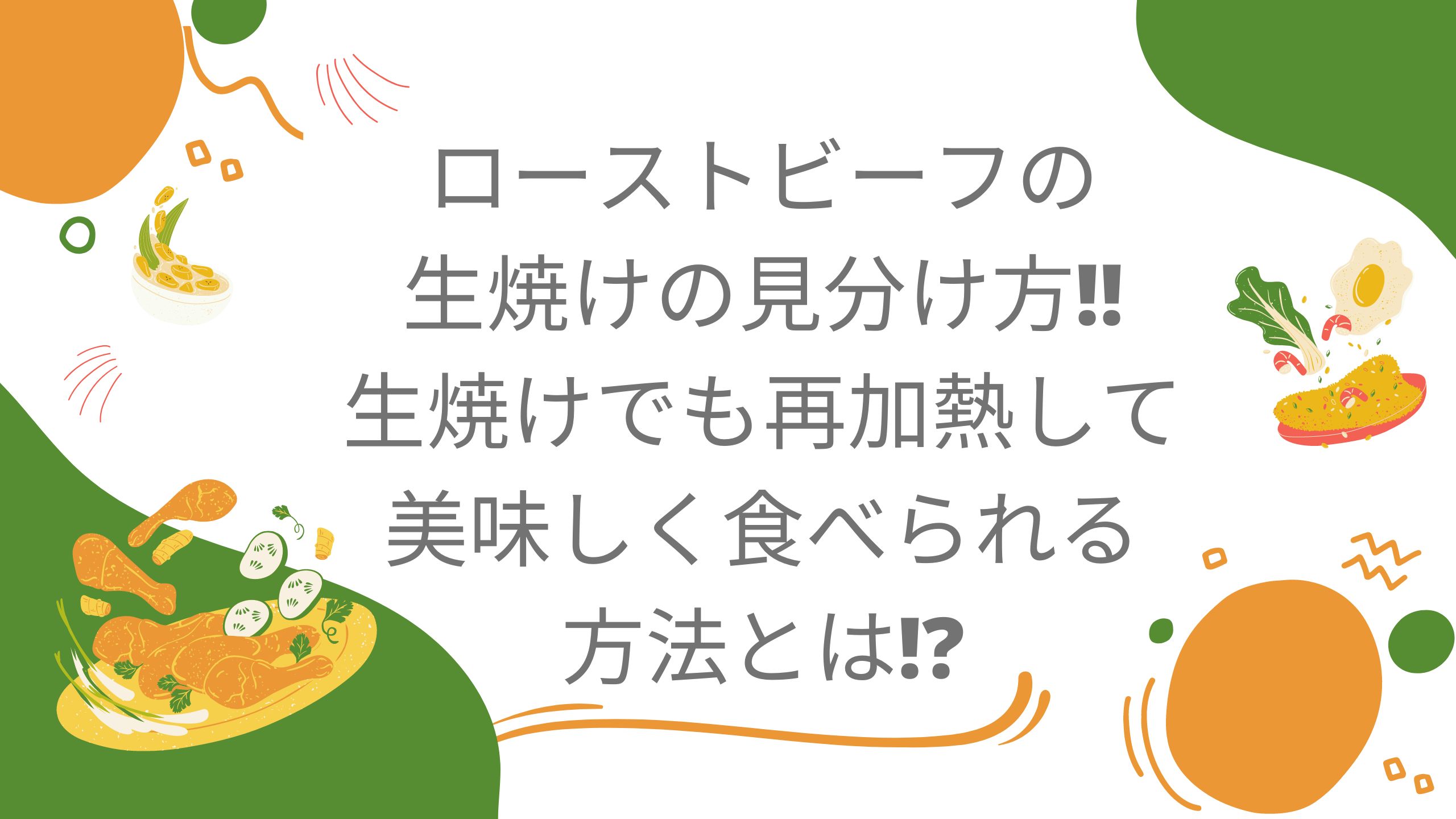

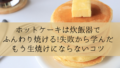
コメント