 ダイエット
ダイエット チラコナは痩せない!?中年太り40代が500円で始めた効果をガチレビュー!!口コミも徹底調査
更年期も始まる40代。 30代までの若かったころに比べて体型も変わり太りやすくなって、肌や髪のつやもなくなり、似合う洋服も変わり・・・。 中でもいち早く何とかしたいのが中年太り!! そう、このお腹にたっぷりと付いた浮き輪のようなお肉のカタマ...
 ダイエット
ダイエット 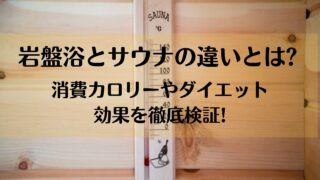 ダイエット
ダイエット 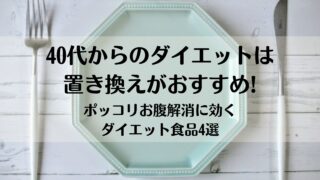 ダイエット
ダイエット 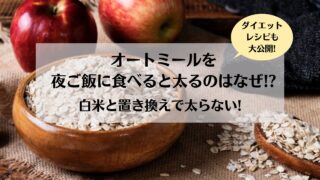 ダイエット
ダイエット  ダイエット
ダイエット 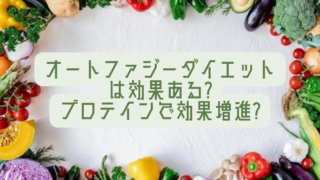 ダイエット
ダイエット 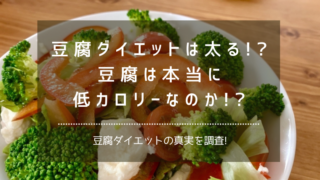 ダイエット
ダイエット  ダイエット
ダイエット  ダイエット
ダイエット 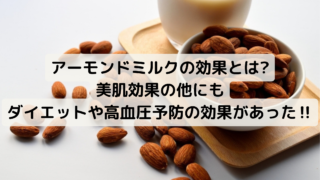 ダイエット
ダイエット